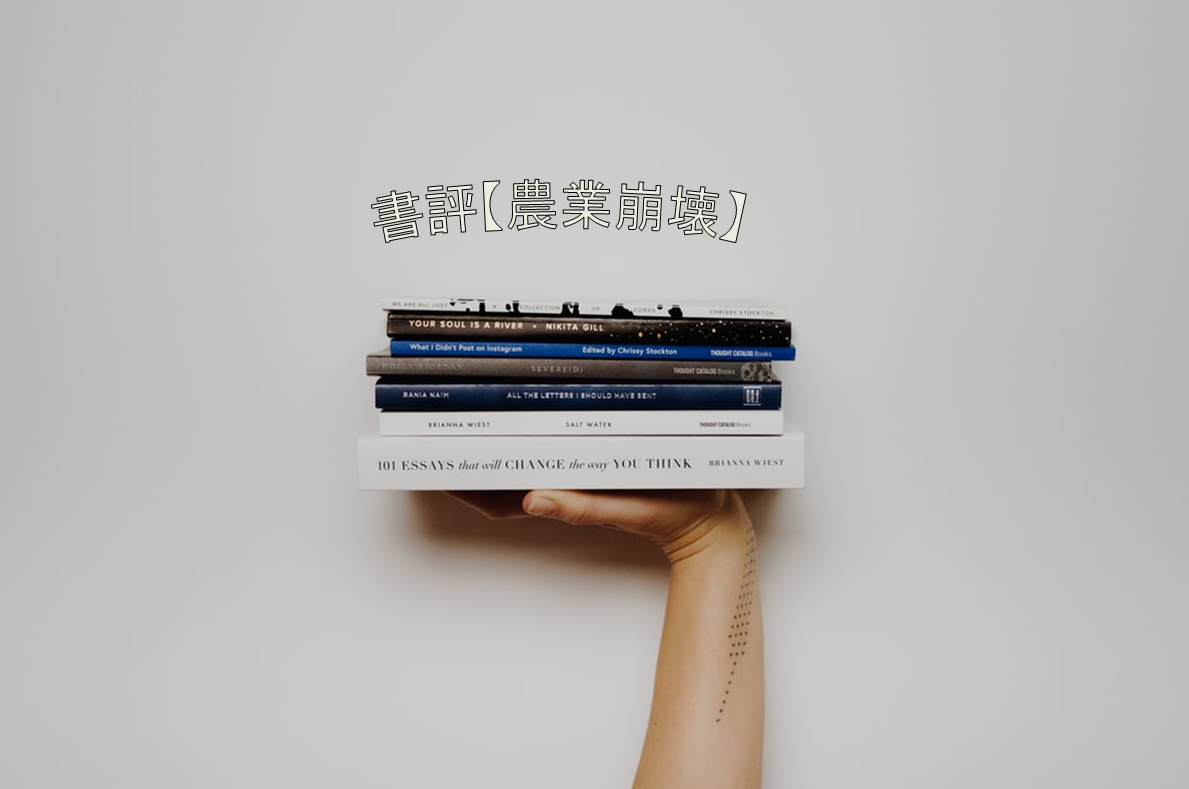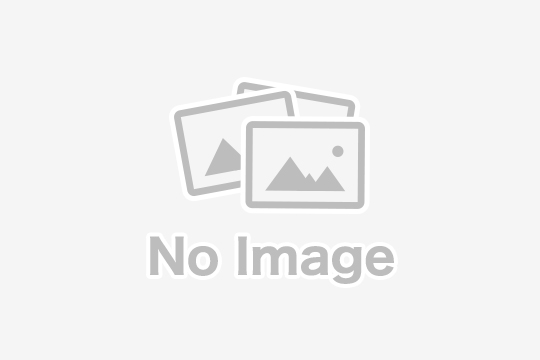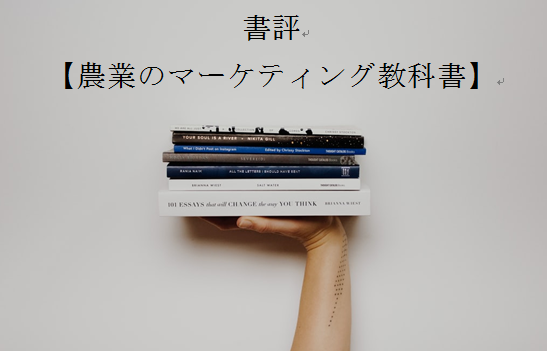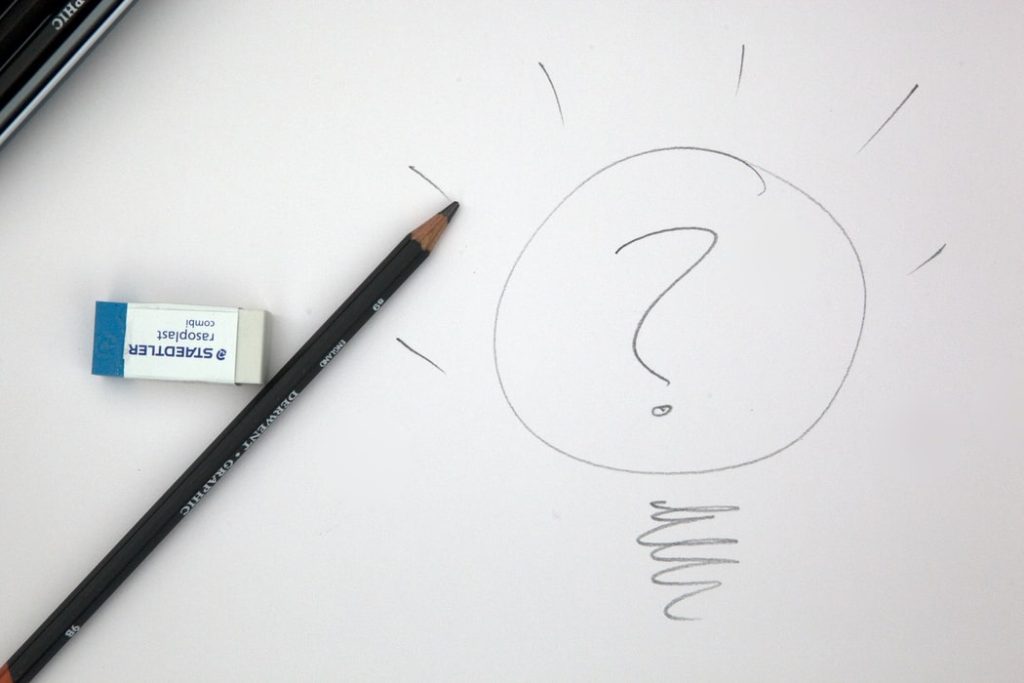
 新米ファーマー
新米ファーマー 研修ってする必要あるの?
研修のメリットって何?
そんな方へ向けて研修の目的や研修でしか得ることのできないメリットについて説明します。
ここでしか出会えないかけがえのない仲間と出会える。
というような青春ドラマの一コマのようなオチではなく、どんな利益が期待できるのか、という観点で書いていきますので安心してください。
研修のメリットはざっくりこの4点です
・いざという時のバイト先として
・機械の借り先として
・土地などの情報のハブ
・資材をもらうため
・人脈形成
・販路の引継ぎ
栽培技術については研修で誰かから教わるか、自分でトライアンドエラーするかで甲乙つけがたいので省いています。
研修という制度は農業に関するぼんやりとしたイメージを具体的にしてくれ、転ばぬ先の杖、困った時の保険的な役割が大きいです。
それでは、それぞれのメリットについて順に説明していきます。
いざという時のバイト先として

独立後、野菜を作って売るだけでは稼ぎが足りないことは十分あり得ます。
研修していた頃と独立した頃で、研修時代には想定できなかったトラブルはよくあります。
雪や台風などの天候不順以外にも、独立後の不慣れな時間の使い方であったり予期せぬ病気や体調不良、計画通りに野菜ができない事は1年目2年目の頃にはよくあります。
そうなったときの備えとして、もしもの時のアルバイト先として研修先を独立後も利用できると保険として役立ちます。
正確な数はわかりませんので実感ですが、新規就農者の4割近くはアルバイトと農業の2足のわらじを履いています。
アルバイトしながらが良い・悪いの話をしたいのではなく、独立前からアルバイトをするという想定を持ち、想定通りアルバイトと農業を行うという方はとても少ないと思います。
計画通りにいかない、予期しない出来事によりやむを得ずアルバイトをしているケースがほとんどです。
このように掛け持ちになった場合、短期的に農業に全く関係のないアルバイトをするより、勝手を知っている以前勤めていたところでアルバイトさせてもらう方が精神的にも平穏に過ごせるでしょう。
機械の借り先として

農業をやっていると、この時期のこの時間にトラクターを使いたい!という計画を立てるかと思います。
そういう時に限って機械が故障してしまうことがあるんです。
慌てて修理に出すと修理屋さんが大忙しで自分の番まで順番待ちでやっと自分の順番が来たかと思えば雨が続いてしなかなかトラクターが圃場に入れない…
こうならないためにも、トラクターが使えなくなった時のカードを持っておく必要があります。
トラクターのような大型機械は一件の農家に1台保有されているところがほとんどですが、シェアして使いたい!と思われる方も多いのではないでしょうか。
大きな組織の研修先であれば組合のようなものを組織し、大型機械はそこで共同購入して利用することをされているところもあります。
このような組織ができれば、トラクターをはじめ、機械の初期投資をかなり抑えることができます。
別々の研修先から集まった新規就農者の集まりの場合、個人の価値観がぶつかり合い機械の共同利用の話がなかなかスムーズにいかないこともあります。
機械に独特なクセがつく、他の人の使い方が気に入らない、やたら気を使ってしまうなどなど、いろいろな理由があるかと思います。
同じ研修先で農業に対する考え方、流派が同じ組合なら、そうした不安を払しょくできそうです。
そのような組合作りの足掛かりとしても、研修先を利用することは有益です。
土地の確保

土地の確保についてはこちらにもまとめてあります。
結論、土地の確保は情報戦です。
土地の情報はどこに集まるかと言うと、声の大きいところもしくは規模の大きいところです。
規模の小さい零細の農家さんや新規就農したばかりの農家さんの元へは、土地をしっかり管理してもらえるかどうかわからない、信頼のない状態のためなかなか土地の情報が回ってきません。
大規模で単一作物を作るといった面積と売上が比例する経営計画である場合、なおさら土地の情報は死活問題です。
研修先の農家さんが研修生を受け入れ続け、規模拡大を繰り返している状況であるならば土地を貸す地主さん側から信頼されている(=実績がある)研修先を選ぶ必要があります。
虎の威を借りる狐の通り、研修先を虎と見立て、優位に経営計画を進めるようにしましょう。
情報のハブ
情報を常に仕入れ、知識をアップデートし続ける必要があります。
独立して経営を行っていく上で最新の農薬の情報や新しく発売された肥料の情報、新しい野菜の品種など様々なアンテナを立てる必要があります。
そのような情報を積極的に取りいれるか、情報が自然に入ってくる仕組みを構築できているか。これはとても重要です。
具体的には農薬メーカーや資材メーカー、種苗メーカーとのパイプがあるかどうかです。
メーカーの営業マンの方とのパイプがあると常に新しい情報に触れることができます。
このような環境を作り、コミュニティに積極的に入り込むことを目指しましょう。
資材をもらうため

これは最も重要です。
農業を始めるにあたってトラクターや軽トラック、ビニールハウスなどの大型設備は、創業融資などでしっかりフォローされるため調達のハードルは低いです。
しかし、収穫コンテナや一輪車などの運搬具、培養土やセルトレイといった苗床苗場の資材、加温ハウスを作るためのビニールや育苗ハウスの防虫ネットなど1アイテムあたりの単価は数千から数万円ではありますが、たくさんの量が必要なもの、どれだけ量が必要かわかりづらいもの、もしかしたら足りなくなってしまうかも知れないものがあります。
これらのアイテムは営農を行っていくうちに自然と集まってくるケースが多いです
しかし、独立した初期の初期には絶対に必要なものです。
そのためまだ売り上げが十分に立たない時にこれらの小物のアイテムがじわじわとお金を奪っていきます。
そのためできるだけ研修先にこれらのアイテムをもらえるような関係を築くことが理想です。
何でもかんでも新品でそろえていたらお金がいくらあっても足りません。
かといって近所の中古農機具屋でそろえても意外にお金はかかってしまいます。
貰えるものは貰いましょう!
人脈
研修先の地域=就農する地域の場合。
よくも悪くも農業の業界には村社会の風習が残っています
やれ誰々に挨拶しなかったとか、やれ誰々に無断で野菜を売ったとか。
こうした非効率的なトラブルに時間を奪われないために地域では誰が力を持っているのか、その人の性格や癖はどんなものなのかを知っていく必要があります。
またそのような名手に気にいられればびっくりするほどスムーズに仕事ができます
研修先の看板を利用してゆっくりとチャリを進めていきましょう
人脈で言うともう一つ青年や4エイチクラブのような団体もあります
これらの団体は地域ごとで性格が異なるため一概に入るべき入ってはいけないなどは言えません
また入るのは簡単ですが抜けるのが難しいと言うシステムになっていることが多いです
自分は入るべきなのかどうか見極める時間を研修中に確保しましょう。
販路の引継ぎ

販路を確保するには多くの時間がかかります
研修先の販路をそのまま使わせてもらうことによりこの時間を短縮ができます
研修先を利用しない場合主な販路としては農協もしくは直売所道の駅などが考えられるかと思います
もし研修先が市場関係に知り合いがいたとしたら、仲卸経由で加工業者に強かったとしたら、スーパー系に強い仲卸が知り合いにいたとしたら、いきなり販路を持った状態で形がスタートできます。
どんなに良い野菜を作っても売れなければ意味がありません。
また、独立して間もない頃は役所や農協への提出書類が山のようにありただでさえ事務処理に追われてしまうこともあります。
できるだけ栽培に集中できる環境を作るため販路をたくさん持っている研修先を探しましょう
番外編:農業はじめる前の就職先
農業をはじめるにあたって、長期間で計画できる方はこのような就職先をおすすめします。
研修前に2-3年以下の企業で働くことでお金をためながら独立後かなり役立つスキルを得られます。
・農機屋で機械周りに強くなっておく
・種苗メーカーで品種特性に強くなっておく
・農薬メーカーで作物の原理に強くなっておく
・ハウスメーカーで最新設備の知識を蓄えておく
実際、これらの企業出身の農家さんは農業技術や販路にオリジナリティーにあふれ、農家歴が浅くても結果を出している方が多いです。
今すぐ農業をやりたい!と思って農業業界に飛び込んだ私にとっては、しっかりとした準備資金とパイプを形成された彼らがうらやましく思っています。
おまけ
私の場合、研修先と就農した地域が異なっていました。
そのため、研修先の地域のJA青年部の活気の良いイメージのまま、就農先の別の青年部に所属しました。
ところが、加入したところはイメージと全然違う活気のない、ただただ時間だけが奪われていくような青年部でした。
就農直後に青年部加入の意思を効かれ、就農先の地域では知り合いが少ないため、コミュニティに所属しておくほうが良いだろうと思って迷わず加入しましたが、馬が合いませんでした。
地域やそこで働く人たち、ご近所さんのクセはその土地に何か月も馴染まないと合う合わないはわからないものです。